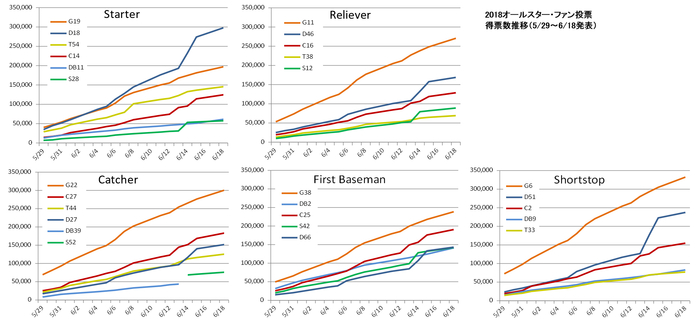想像以上に酷い、と蔵馬は眉をひそめた。この街に足を踏み入れてから既に一時間以上歩き回っている。砂埃と死臭の混じった不快な空気の中を進みながら蔵馬は訝っていた。この街には、最早一つの生命も残っていないのか。
「皆、死に絶えてしまったんでしょうか?」
彼女の思いを見透かしたように、隣を歩く青年が久々に口を利いた。蔵馬の腹心の部下・楠樹だった。
「かもしれないな。」
溜め息と共に蔵馬が答えた。魔界一の勢力を誇る盗賊団の総長とその片腕がこの廃墟を訪れた本来の目的は、街の何処かに眠る古代都市の隠し財宝……だったはずなのだが、あまりの惨状に二人ともすっかり当初の用件を忘れてしまっていた。
「信じられない、ひと月前までは三十層でも最も栄えていた都市だったのに……」
「躯の軍隊にやられたらしい。馬鹿な奴らだ、大人しく服従していればここまで悲惨な目に遭わずに済んだだろうに。」
「意に沿わぬ同盟を結んだら、躯の手足に成り下がるだけでしょう。」
「たとえ屈辱に甘んじることとなっても守らねばならないものがある。治世者がそれを忘れていいはずがない。」
「……」
楠樹は口をつぐんだ。いつもは女性のような美貌に不釣り合いな剛胆さを見せる彼が、この街に入ってから何かに怯えている。声にこそ出さぬものの、顔は蒼くうつむいたまま歩いている。それを見かねて蔵馬が声をかけた。
「昔を思い出すのか。」
「えっ? いえ、別に……」
楠樹がうろたえ、首を振った。大貴族の跡取り息子として生まれた彼が、戦火で家族と家を失い盗賊団に合流したのはもう百年も昔のこと。しかし、当時まだ幼かった彼の精神的外傷〈トラウマ〉が容易く消えるものでないことは蔵馬とて充分に承知している。
「少し休もうか。」
「済みません……」
消え入りそうな声で答えた楠樹を、蔵馬は大きく割れた石壁の陰へと誘った。かつてこの街の繁栄を支えてきたのはこの壁……今や瓦礫となってしまった巨大な城砦だった。山のようにそびえていた城砦をここまで粉々に破壊する軍隊とは、如何ほどの戦闘能力を誇るのだろう。出来ることなら正面衝突は避けたいと、蔵馬は冷静に思いを巡らした。竹の水筒から水を一口飲み、楠樹は深々と息を吐いた。
「凄まじいですね。オレの故郷も戦で壊されたけど、ここまで惨くはなかった。」
「ここまでするのは只の八つ当たりだ。優れた人材と発展した文化、それを全部破壊するなんてあまりに頭が悪すぎる。」
「御頭、これだけ凶暴な躯が女だってのは本当なんですか?」
「本当さ。だから時々ヒスを起こす。オレを見てれば分かるだろ?」
蔵馬の冗談に楠樹もようやく笑顔を見せた。が、やはりいつもより弱々しい表情だった。
「どうする、もう帰るか?」
「そうですね。生存者もいませんし、この状態では目的の物が残っているとは思えませんし……」
「とんだ骨折り損だったな。まあ仕方ないさ。」
蔵馬が立ち上がり、楠樹も後に続いた。元来た道を辿り、二人は外れの森で待つ仲間達の元へ足を速めた。楠樹は死の影色濃く漂う街を一刻も早く立ち去りたい様子だったが、蔵馬は先と変わらぬ足取りで歩を進めた。彼女がこのような惨状を目の当たりにするのは実は初めてではなかった。
†
『酷い……』
思わず漏らした言葉に、隣の男も頷いた。
『本当に、ここまでするかよ。』
遠い昔、蔵馬は今は亡き親友・黒鵺と共に廃墟の街を訪れていた。今以上に混沌とした時代だった。群雄割拠の戦乱の世、幾つもの都市が興り滅びていった。魔界の覇権を争う者達の陰で、弱い命がいくつも使い棄てられ消えていった。二人が足を踏み入れたのはそんな中で生き残れなかった小さな街の跡……吹きすさぶ風と砂塵の舞い上がる音以外、何も聞こえない静寂の場所だった。あまりに空虚なその光景に、蔵馬は激しい衝撃を覚えた。
『どうして、こんなことに?』
『この魔界が誰の物か、まだ決まってないからさ。』
動揺する蔵馬とは裏腹に、黒鵺は冷静だった。
『それはそうかもしれないけど、でもそれって、本当に決めなければいけないことなのか?』
『さーな。でも、それをみんな決めたがってる。魔界を是非、自分の手にってな。』
そう言いながら黒鵺は、足元の小石を拾いひび割れた石の壁へ向けて投げつけた。辛うじて形を保っていたその壁は、小石一つの衝撃でがらがら音を立てて崩れ始めた。
『結構、風化も進んでるな。』
黒鵺が肩をすくめた。
『勿論、オレは誰かが魔界を独占するなんてアホらしいと思うぜ。だけどこんな状態が続くのも嫌だし、力任せの成り上がりにどうにか出来る世界じゃない。アホに牛耳られるくらいならオレとお前で魔界シメちまおうって、そう思ってるだけ。』
『解ってるよ。オレもお前も欲しいのは権力じゃない。闘わなくても生きていける世界なんだ。』
蔵馬が答え、黒鵺が頷いた。と、蔵馬はふと二人の数歩先に“生きているもの”を見つけた。
『あ……!』
瓦礫の中にたった一輪、小さな花が咲いている。駆け寄った蔵馬は、廃墟の中で初めて見つけた生命をいたわるように両手で包み込んだ。
『こんな廃墟の中で……花が咲いてる。』
『本当だ。』
黒鵺も近づいて小さな花を覗き込んだ。淡い紅色の花片が彼の動きに合わせて揺れた。
『すげぇな、これだけ破壊されて粉々になっても命は再生する。廃墟に根を下ろして花を開き、新しい命を生む。そしていつかこの廃墟を覆い尽くす日がきっと来る。』
『そしてその時はきっと、またこの街に人が戻ってくるんだ。』
『ああ。』
黒鵺が微笑った。
『どれだけ打ちのめされても立ち上がる力を持っているんだ、花も人も。』
そう言いながら彼はそっと指を伸ばし、傷つけぬよう注意深く花に触れた。
『でもな蔵馬、』
『何?』
『……』
黒鵺が何かを呟いた。蔵馬が頷いた。二人はいつまでも、小さな花をじっと見つめていた。
†
「! 御頭、あれ……」
突然楠樹が声を上げ、蔵馬は意識を引き戻された。彼が指さす方向で一瞬、何かが動いた。
「生存者が!」
「!」
瓦礫の中を動く人影がいる。蔵馬が走り出し、楠樹が後を追った。廃墟の陰に佇んでいたのは何と、年の頃十そこらと思われるまだ幼い少女だった。
「おい、こんな所で何をしているんだ?」
蔵馬が声をかけた。少女は怯えたように顔を上げた。顔は薄汚れ、服はボロボロだった。腕には大きな傷の痕があり、満足な治療も受けられぬままに塞がったためか皮膚が醜く引きつれていた。
「他に誰かいないのか? 家族は?」
「……家族は、いません。みんな、死んじゃったから。」
少女が答えた。蔵馬は身をかがめ、彼女と同じ高さに視線を合わせてその顔を覗き込んだ。
「どうしてこんな所に留まっているんだ。食べ物だってろくにないだろうに。」
「大丈夫です、私の分くらい。」
「でも、お前くらいの子供が一人でいていいはずがない。」
「他に行く所もないから……。」
そう言いながら少女は首を振った。と、蔵馬は彼女が手にしている意外な物に目を留めた。それは小さな熊手と、まだ若い植物の苗木だった。
「それは?」
「庭に生えてたんです。母さんが、ずっと大事に育てていた木。だから、もっと広い所に移してあげようと思って。」
「『移す』?」
「沢山のおうちに生えていた方が淋しくないから。」
蔵馬はじっと苗木を見つめていた。その眼差しが次第に遠くなった。ふっと表情を和らげ、彼女は連れを振り返った。
「楠樹、お前先に帰れ。」
「は? ……えっ!?」
蔵馬は再び少女に向き直り、優しく尋ねた。
「まだ苗木はあるのか?」
「え、はい。庭にまだ木とお花が。」
「オレも手伝うよ。そういう訳だ、先に帰ってろ。」
「ちょ、ちょっと待って下さい! オレもやりますっ!」
楠樹が慌てて遮った。蔵馬が笑った。
†
風も凪に入り、廃墟の街には静寂が訪れていた。帰り道、自陣へ戻る道すがら、楠樹が遠慮がちに尋ねた。
「御頭、あの……どうして、あの少女を手伝おうと思ったんですか?」
蔵馬が振り返った。
「それに貴女なら、ちまちま植え替えなくてもあの苗を大きな森へ変えることくらい造作ないでしょうに。」
「馬鹿言え、この街を再生するのはオレじゃない。あの子と、あの子が植えた植物なんだ。」
蔵馬が静かに答えた。楠樹はしばらく考えていたが、ふと足を止めて廃墟の街を振り返った。
「何だかオレ、分からなくなってきました。」
「何が?」
蔵馬も振り返った。楠樹はじっと、瓦礫となったかつての城砦を見つめていた。
「オレ達は今、『この世を変える』なんて言いながら魔界の勢力争いしてるわけですよね。でも、オレ達が必死になったところでなかなか世界は変えられない。弱い物は虐げられ、何度も何度も打ちのめされている。だけど彼らはその度に自力で這い上がるんです。だったら、オレや貴女が今闘ってるのは一体何のためなんだろうって。」
「お前がそんなことで迷うなんて、不思議だな。」
蔵馬が笑った。
「オレ達が闘ってるのは、お前のような思いをするヤツが二度と現れないようにするためだ。傷ついても立ち上がる、その通りさ。だけど、お前だって本当は、傷つきたくはなかっただろう?」
「…… ええ。」
楠樹が頷いた。蔵馬が微笑った。記憶の中で、あの時の黒鵺の言葉が甦る。
『この花が、二度と傷つかないといいな。』
……そう呟いた、彼の声が。
「考えすぎは良くないぞ。さあ、帰ろう。」
姉が弟を諭すように、蔵馬はとん、と楠樹の肩を叩いた。
【完】